精進坂

参道から一の鳥居に向かう坂道を精進坂と呼びます。
この写真は三十三式年祭の朝の様子です。

平時の静かな精進坂はこんな感じですね。
白山神社の標柱

坂の右手に白山神社の標柱が立てられています。

おそらく懸社白山神社と刻まれていたのが「懸社」の部分が埋められて消されています。
県社とは何??
県社とは?
AI による概要
「県社(けんしゃ)」とは、かつての神社の社格の一つで、国幣社や官幣社よりも下、郷社よりも上の社格を持つ神社のことです。県から奉幣を受けた神社を指します。
詳細:
- 社格:明治時代から第二次世界大戦終結まで存在した、神社を格付けする制度における社格の一つ。
- 奉幣:幣帛(へいはく:神に捧げる布や品物)を奉る儀式。
- 位置づけ:国幣社や官幣社は国や政府から直接奉幣を受けるのに対し、県社は各都道府県から奉幣を受けました。
- 廃止:第二次世界大戦終結後、社格制度は廃止されました。
- 例:愛知県半田市の神前神社は、旧県社であり、地元では「県社」と呼ばれて親しまれていました。また、福島県いわき市の子鍬倉神社は、通称「けんしゃ」と呼ばれています。
つまり、「県社」は、かつて存在した神社の格付けにおける特定のカテゴリーを指す言葉です。
なるほど、第二次対戦後に廃止されて懸社の部分のみを埋めて消したというわけなんだねぇ、、、。
霊應山顕海寺

標柱の反対側には小さなお寺があります。
お寺の名前は顕海寺です。

石段を登ってみます。
六地蔵

石段の右手には六体のお地蔵様が並んでおります。
六体並んでる意味は??
AI による概要
六地蔵(ろくじぞう)とは、仏教における地蔵菩薩を指し、特に六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間道、天道)のそれぞれに現れ、迷える衆生を救済するとされる六種類の地蔵菩薩の総称です。これらの地蔵は、それぞれの道で苦しむ人々を救うために、異なる姿や名前で現れるとされています。
六地蔵の種類と役割:
- 檀陀地蔵(だんだじぞう)::地獄道を救う。
- 宝珠地蔵(ほうじゅじぞう)::餓鬼道を救う。
- 宝印地蔵(ほういんじぞう)::畜生道を救う。
- 持地地蔵(じじじぞう)::修羅道を救う。
- 除蓋障地蔵(じょがいしょうじぞう)::人間道を救う。
- 日光地蔵(にっこうじぞう)::天道を救う。
六地蔵の祀られ方:
六地蔵は、一般的に6体の地蔵菩薩が並んで祀られています。これらの地蔵は、寺院の入口や墓地の入口、村境や辻など、人々が出入りする場所に置かれることが多いです。これは、六道の世界を旅する人々を導き、守護するという意味が込められています。
AI の回答には間違いが含まれている場合があります。
たしか、白山の山頂付近にも六地蔵跡という場所が存在していたはずです。
お池巡りコースを歩くと通るんじゃなかったかな?
顕海寺本堂

本堂は簡素な作りで装飾等も控えめな感じです。
顕海寺概要
天正2年(1574)、織田信長による越前攻めにより越前守護職の朝倉氏(本拠:一乗谷)は大名家から没落した事で越前国内の勢力の均衡が崩れ一向一揆勢が平泉寺の境内を占拠しました。
その際、多くの堂宇、寺宝、記録などが兵火により焼失し平泉寺は大きく衰退します。
顕海寺の創建は天正11年(1583)、時の権力者である豊臣秀吉の許しを得て顕海僧正が平泉寺を再興した際、跡地に草庵を結び顕聖院と号したのが始まりと伝えられています。寛永15年(1638)に堂宇を建立し寺号を顕海寺に改めます。
寺宝である銅造阿弥陀如来坐像は鎌倉時代に製作されたもので、像高520cm、金銅仏、天正2年(1574)一向一揆の際、顕海僧正が池の中に隠していたとの逸話が残っています。
銅造地蔵菩薩立像は鎌倉時代に製作されたもので、像高641cm、金銅仏。
両仏像とも昭和52年(1977)6月17日に福井県指定文化財に指定されています。本堂は入母屋、桟瓦葺、平入、桁行7間、正面1間向拝付。
https://www.fukureki.com/hakusan/ken.html
宗派:天台宗。
本尊:阿弥陀如来。
この説明だけではちょっと概要は掴みにくいかもしれません。
顕海僧正のところでもう少しわかりやすく解説します。

霊應山の扁額が掲げられています。
本像阿弥陀如来の縁起

当山畧縁起 と書かれた板が置かれています
略縁起と理解すれば良いのでしょう。
最初の方を飛ばしながら読んでみます。
開基 泰澄大師
天台別院の寿号を賜う
比叡山の末寺となる
天正二年二月 六千の坊舎尽く焼亡す
同十一年 故学頭顕海僧正当山に帰り一の草庵を結び賢聖院と号す
寛永元年 之に居る
同十一年 一寺を建立し顕海寺と号す 以后現在に至る
本尊阿弥陀仏は賢聖院の本尊として天正年中兵乱の際 専海 日海の二弟子該井中に投じ
顕海僧正と共に美濃?学院に逃げる
天正十一年 帰錫直に井中より上げ 顕海寺本尊とする
ところどころ読み違いがあるかもしれません。
ここで重要なことは、顕海寺の本尊阿弥陀如来は顕海僧正が平泉寺が一向宗により焼き討ちにあうことを予見して、弟子の専海日海に如来像を井戸の中に沈めて隠すように命じて、落ち延びて、天正十一年に帰って来た時に井戸から引き上げてこの寺の本尊とした。
そのように伝承されているということですね。
北向きわらべ地蔵

新しいもののように見えますね。
山門と鐘楼

山門の脇に鐘付き堂があります。
地蔵堂

地蔵堂です。
おそらく中にたくさんのお地蔵様が並んでいるんじゃないでしょうか?
越智山にも地蔵堂がありました。
顕海廟

地蔵堂の裏手には顕海僧正のお墓だと思われる廟があります。
顕海僧正とは何者か?
平泉寺白山神社のHPによると
勢力が大きくなるに従って平泉寺内部には不和が生じ、折から係争中の一向一揆勢力によって、当社は天正2年(1574)全山焼失しました。
https://heisenji.jp/hakusan-shirine/about/
実力者であった宝光院と玉泉坊兄弟の仲が悪く、有力者朝倉氏滅亡の危機に際し、兄弟それぞれの思惑も手伝って平泉寺は分裂し争いました。
そして、ついには五キロほど離れた村岡山(むろこやま)の方に出陣していた隙をつかれて、村内に侵入した一揆勢の手によって放火され、当社は自滅するように灰燼に帰したのでした。
この事態を予見していた平泉寺の学頭賢聖院(げんじょういん)顕海(けんかい)僧正は、専海(せんかい)・日海(にっかい)のお弟子二人に、急いで重要で持ち運びのできるものをまとめさせ、九頭龍川上流の越前美濃国境付近の桔梗原(ききょうがはら)に落ちのびました。
そして、そこに住んでいた原家(はらけ)の世話になりつつ雌伏すること十年、天正11年(1583)春、頃合いを見計らって三人は平泉寺に帰山しました。
一面は焼け野原のままでしたが、旧境内の一角に廬(いおり)を営み再建に着手しました。
有難かったのは、豊臣秀吉がすみやかに朱印状を下し、平泉寺そのものが安堵されたことです(秀吉の庇護を受け安心して生活することができました)。
中宮平泉寺は一向宗により全山焼き討ちに遭い一旦滅亡します。
なぜ?6千もの坊舎を構える平泉寺が簡単に焼き討ちにあったのか?
そこには勢力が大きくなりすぎたための内部分裂があったわけです。
それを予見していた学頭顕海僧正が弟子達とともに一旦落ち延びて、後に焼け野原に戻り、平泉寺を再興し、さらに白山山頂での祭礼奉仕をそのままつづけることを実現しました。
顕海僧正は中宮平泉寺にとってはヒーローだったんですね。
再興した当初は賢聖院という草庵を拠点にしていたようですが、後にそこは弟子の専海に譲り隠居寺としたのが顕海寺というわけです。
作りが質素なのは隠居寺だからなんでしょう。

精進坂に戻ります。

精進坂から見た顕海寺。

外側から見た山門です。

精進坂を登ってゆきます。
精進坂についての云われ

昔はこの坂より上には魚の持ち込みは禁止されていました。
https://heisenji.jp/map/
菩提を求めて身を清め慎むということで「精進坂」と呼ばれてきました。
この坂から上は魚など生臭ものの持ち込みは禁止されております。
一の鳥居

式年大祭の日の一の鳥居。
精進坂を登ると一の鳥居が見えて来ます。
これは式年大祭の日の様子。

普段はこんな感じですね。
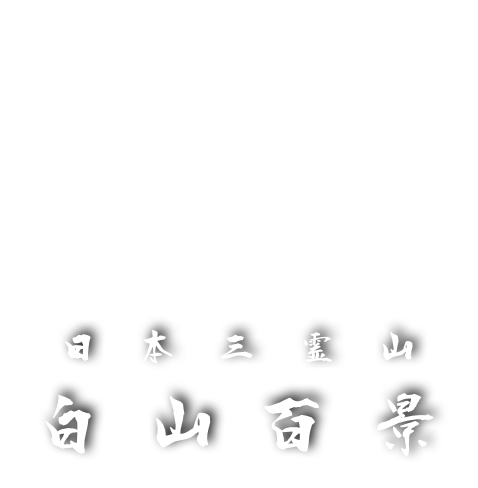
















コメント